『放蕩息子』―蕩児から、父へ
そんなわけで、ヘンリ・ナウエンの『放蕩息子』を読み終えたわけだが。
前回で、自分を「弟息子」にたとえるのは簡単で、よくできた兄息子に重ねたときに気づく霊的課題に挑むことは難しいなぁということを書いた。
だがナウエンは、その後、さらに困難な霊的課題へと召命があることに気づいた。それは、「父(神)」であることに近づこうとするものだ。
人は、神の似姿とよく聖書ではある。しかし、顕教としてのキリスト教において、神に近づこうとすることは、ある意味タブーなんだ。
神とは絶対者であり、いと高きものであり、「教会」を通して帰依する存在だ。
だが、ナウエンにとって「神」とは「放蕩息子」に描かれるとおり、与えて与えて、なお与えつくす、母性であり、父性である全なる愛としての存在だ。その象徴としての父だ。
父は、弟息子が放蕩の限りを尽くして異邦にあるときも、家にいて、ただただ待っていた。すべてを与えて迎えるために。たとえ、弟息子が自分に反逆していたとしても。
父は、兄息子が従順な姿勢で日々まじめに働くのを見つめて、「わたしのすべてはおまえのものだよ」とすべてを与えた。兄がそれに気づかず、自由奔放に生きた弟をねたんでいたと知っていても。
ナウエンは言う。
「わたしは自分が父であるという召命の真実をはっきりと自覚しているが、それと同時に、それに従うことはほとんど不可能のように思える。他の人がみな、さまざまな欲求、あるいは怒りに駆られて外出しているときに、自分だけ家にとどまっていたくない。
わたしも同じ衝動を感じ、彼らと同じように自由に動き回りたい! しかしそうなれば、いったいだれが家に残るのか?
人々が疲れ果て、憔悴し、興奮し、落胆し、罪責感を抱き、肩身の狭い思いで帰って来るとき、誰が迎えに出るのか?
要するに安らぎの場があり、抱き留めてくれる人がいることを、だれが納得させることができるのか? もし、わたしでないなら、だれがそれをするのか?」
息子たちに自分をたとえて、課題に取り組むことは簡単だ。息子たちとは、「未熟者」なのだから。だが、神であり、全なる愛である象徴としての父を自分に課するという決意。
それは、神秘主義でいえば、まさに神人合一へと続く霊性の道をナウエンが歩み始めたことを意味する。
神は、神になるために人になった。というオレさまの好きな公理があるんだが、ナウエンは、人の身でありながら、神の愛をその身で表現する、もっとも困難な道を選んだのだ。
弟息子、兄息子、そして父へ。
蕩児として帰還する者から、永遠に「そこ」にいて、無条件に、そして永遠に迎え入れ、与え尽くすものへ。
それが、ナウエンの追求したキリスト教霊性の道だった。
レンブラントの『放蕩息子』に出会ってから、ナウエンの霊性の道は、まさに蕩児から神へと向かう一直線の困難な道のりではあった。
だが、その道筋は、どんな暗闇に陥っているときであっても、つねに内なるキリストの光に照らされ、その声に励まされていたに違いない。
ナウエンの100分の1でも、その真摯さをもって、道を歩いていけたら。そう思わずには、いられない。蕩児であることを選びたがるオレさまでは、父たることを最後に選んだナウエンは、まぶしい。
ま。そんな話だ。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はいはい。そんなワケで。オレさま主催の『神秘学講座 基礎編』の案内だ。
↓ここ見ておくんなまし。参加してみっか、という奇特なヤシはどうぞ。
第一期受付は2月いっぱいまでです。
神秘学講座 基礎編 参加要綱はこちら
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

せっかく来んだから、押しておけって、コレ。(藁↓
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)

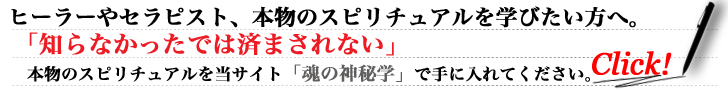














この記事へのコメントはありません。